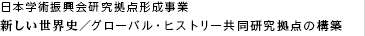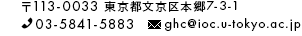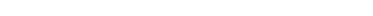2019.10.19
GHC Summer School 2019 (1/2)
報告1
2019年9月2日(月)午後に、東京カレッジ・シンポジウム「グローバルヒストリーはなぜ必要なのか?」が開催されました。ミヒャエル・ファチウス氏(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)が司会を務め、パネリストとしてセバスチャン・コンラート教授(ベルリン自由大学)、マルク・エリ氏(フランス国立社会科学高等研究院)、シェルドン・ギャロン教授(プリンストン大学)、鈴木英明氏(国立民族学博物館)が登壇しました。
羽田正教授(東京カレッジ)によるシンポジウムの趣旨説明、司会のファチウス氏によるパネリストの紹介に続き、4人のパネリストがそれぞれの知見からグローバルヒストリーの必要性について議論しました。
まず、ドイツ、西ヨーロッパの歴史、日本の歴史に関連する研究を展開するコンラート教授は、グローバルな要因によって形づくられるナショナリズムの事例としてドイツのナショナリズムを挙げ、グローバルな視点で各国の歴史を理解する必要性を提言すると同時に、グローバル化の中でも国家の歴史がなくなるわけではないと論じました。
次に、ソ連、カザフスタンの環境の歴史と土壌科学に関する研究を行うエリ氏は、冷戦における環境科学の歴史をグローバルヒストリーというアプローチを用いて分析しました。冷戦によって分断された世界で、東西のブロックがお互いにどう対立し、協力したのか、さらに、競争ゆえに協力が進んだことを明らかにするためにはグローバルヒストリーが必要であるとの見方を提示しました。
続いて、近代日本史、比較、越境、地域歴史、日本、ドイツ、イギリスの第2次世界大戦史について多くの著作があるギャロン教授は、トランスナショナルヒストリーとグローバルヒストリーの共通点と差異を説明しました。その上で、自身の研究テーマである貯蓄を事例に挙げ、日本の歴史をズームアウトして広い視野から比較・検討することで、ヨーロッパ、アメリカ、そしてアジア諸地域との関連性が明らかになると述べました。
最後に、インド洋史を専門とする鈴木氏は、グローバルヒストリーをボーダレスな国境なき世界における一つの反応と位置づけ、今日の世界においてボーダレスな地球や世界を想像することが容易になった反面、あらゆる境界が依然として存在することに注目しました。また、海域史におけるネットワークの概念を挙げ、「境界」について再検討し、自分たちと世界の繋がり方を模索するためにもグローバルヒストリーが有効であると論じました。
シンポジウム後半では、フロアからの質問を交えてディスカッションが行われました。まず、パネリストの互いの研究にはどのような繋がりがあるのかという点で、エリ氏はそれぞれの発表が国境や境界を疑問視していると指摘し、鈴木氏は従来の歴史研究が用いてきた空間の区切り方を再検討し、私たちがどうやってこの世界を捉えなおすのかが課題であると述べました。さらに、歴史学と政治の関係、そして広くは博物館の展示や教育といった一般へのアウトリーチについての問題について積極的に意見が交わされ、日本、ドイツ、フランス、アメリカ、それぞれの学術界における課題が確認されました。
(文責:寺田悠紀)
報告2
2019年9月2日から、今年度は東京大学にて「第5回GHC サマースクール」が開催された。これまで4回のサマースクールで開催地が4拠点を一巡したため、東京拠点では2度目の開催となる。今回は東大内の伊藤国際学術研究センター3Fが会場となった。各人が事前に配布したペーパーをもとに5分程度で要旨を口頭説明した後、その内容と今後の研究の発展について質疑応答形式でディスカッションを行った。
1日目午前は、ベルリン自由大学のSebastian Conrad教授が司会を務めた。寺田悠紀氏(東京大学)の”Museum and “Iranian Art” Revisited from the Perspective of ‘Exile’”と題した論文は、博士論文の構想を目次とともに提示した。イランのミュージアムの誕生と変容をとおして、ナショナル・アイデンティティの形成をたどる博士論文の計画であった。研究視角を示す語としてExileを使ったのに対して、質疑ではDiasporaやRefugee、Contact Zoneなどの概念との区別について質問とコメントが交わされた。
Disha Karnad Jani氏(プリンストン大学)は、”Unfreedom and Its Opposite: Towards an Intellectual History of the League Against Imperialism, 1927-1929”と題する原稿を発表した。1927年にベルギーのブリュッセルで創設された反帝国主義同盟という国際組織に注目することで、当時の知識人にとっての反帝国主義運動の様相をあきらかにしようとする研究計画であった。質疑では、今後あつかう予定の知識人の範囲について質問があったほか、原稿に引用された政治パンフレットの画像をめぐって使用言語と読み手の関係について議論が盛り上がった。
【2日目午前の発表(Valerie・Pablo)】 2日目午前は、東京大学の山本浩司教授が司会を務めた。Valerie Durieu氏 (EHESS)の原稿の題名は”The Use of Films in Official Information Services in the 1950s—A Global Perspective”であった。Valerie Durieu氏は、博士論文の執筆にむけて、NATOが1950年代から90年代まで作成していた短編映画のフィルムを分析して、国際連盟などの作成した映画との比較を提示した。質疑では、主たる史料として用いたNATO作成の映画フィルムについてミリ数や時間、使用言語などを掘り下げる質問があった。くわえて、NATO映画に込められた思想的な意味やジェンダーの問題について活発な議論が展開された。
Pablo Pryluka氏(プリンストン大学)の原稿の題名は、”Advertising Pinochet: The History of a Global Failure”であった。この原稿は博士論文執筆中に発見した資料をもとにして書かれたもので、博士論文とはべつの単独の論文として発表を目指している。Pablo Pryluka氏は、広告代理店のJ・ウォルター・トンプソン(J. Walter Thompson; JWT)がアルゼンチンでピノチェト軍事政権のイメージ向上を業務として請け負っていたことに注目して、当時の書簡を史料として当時の状況を生々しく再現した。原稿に対しては、この広告代理店のアルゼンチンでの活動の意義づけについて議論が交わされたほか、論文化にむけて投稿先をふくめ具体的なアイディアやアドバイスが出席者(とくに教員)から数多く提示された。
(文責:内田力)