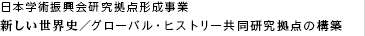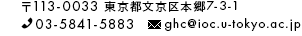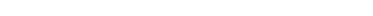2019.10.19
GHC Summer School 2019 (2/2)
報告3
2019年度のGHCサマースクール3日目は、シェルドン・ギャロン教授(プリンストン大学)の進行で、学生の研究発表から始まりました。このセッションは、東京大学本郷キャンパスの伊藤国際学術研究センター中教室(3階)で行われました。
午前に3人の大学院生から発表がありました。それぞれが自分の研究の主たる目的と概要を5分で話し、その後55分は発表者と他の参加者全員による質疑応答とディスカッションという形で進められました。
最初に、内田力氏(東京大学)が”History-Writing and Engagement in the Early Cold War Era: Communist Influences on Japan”と題する論文について発表しました。博士論文の一部をベースに、共産主義が日本の歴史家に及ぼした影響を跡づけ、歴史学者・網野善彦を例に挙げて日本共産党と歴史家の関係を考察しました。参加者からは、網野個人の言説を、その当時の共産主義の影響に関するグローバルな比較研究の文脈でどうとらえるのかというコメントが複数ありました。また、網野のそうした言説を論文の中でもっと強調する手法についても発言がありました。
次に、Oscar Broughton氏(ベルリン・フンボルト大学)が”Redefining Reconstruction”と題する論文について発表しました。研究テーマは、第1次世界大戦後のナショナル・ギルド連盟(1915~23年)の活動と、同連盟がイギリスにおける戦後復興の意味をどう再定義し、他国に拡散させたかということで、5分間の論文紹介後、他の参加者がコメントや質問をしました。「ギルド社会主義」という現象を国際的またグローバルな文脈でより的確にとらえるにはどのような方法が可能かについて質問が集中しました。この現象はイギリスに定着しなかったのに、なぜ、いかにして他の国に広がったのか。国際的なアクターは誰だったのか。ナラティブの方向を、ギルド社会主義がイギリスから他の国にいかにして広がったのかという視点から、この国際的な、グローバルな現象が、論文で取り上げられた他の事象とともに、なぜイギリスで生起したのかという視点へと、構成し直してはどうかという問題提起もありました。
Ael Thery氏(フランス国立社会科学高等研究院)は、”Food Safety, Hygiene Rules and “Moral Qualities” (Suzhi) in Professional Kitchens in Contemporary China: “Cleaning Bad Practices.”“と題する論文について発表しました。この論文は中国における料理人という職業を取り上げ、厨房における食の安全、衛生、倫理問題に関して外国から課されるルールや規範と、国内で定められたルールや規範との相互関係を明らかにしようとしました。論文の組み立て方について、また、ナラティブや詳細な実証的分析によって中国の料理や厨房に関するさまざまなステレオタイプをいかに脱構築しうるかなどについて、質問や意見が出ました。さらに、この研究は厨房における「正式なルール」に焦点を当てているが、ルールだけでなく、日々の慣行や暗黙知、それらの相互関係に関するナラティブも可能ではないかという提起がありました。参加者は、研究テーマに関するローカルな考察をいかに国際的な文脈へ展開させていくかについても意見を交わしました。
(文責:Bee Yun Jo)
報告4
4日目午後のセッションでは、18世紀後半から19世紀を対象とする二つの報告が行われた。司会は、Andreas Eckert教授(ベルリン・フンボルト大学)が務めた。
最初は、Megan Armknecht氏(プリンストン大学)が、”Diplomatic Households and the Foundation of U.S. Diplomacy, 1789-1870”というタイトルで報告を行った。19世紀中葉まで、アメリカの外交システムは十分専門職化されておらず、しばしば外交官の家庭/家族(households)が重要な役割を果たしていた。本報告は、合衆国の外交システム形成期に家庭が果たした役割を、19世紀のさまざまな時期・地域の事例研究を積み重ねて描く試みであった。ハイポリティクスとして捉えられがちな外交史に、ジェンダー・家族の視点を導入することで、権力や権威、帝国に関する理解を変えるとともに、19世紀アメリカの外交の実態に迫ることが意図されている。質疑応答では、家族の世代交代をどのように評価するか、その後の外交官の専門職化に家族がどのような影響を与えたか、アメリカ例外主義を超えてグローバル・ヒストリーのなかに本研究を位置付けるならば、どのような可能性があるかなどについて、議論が行われた。
続いて、森井一真(大阪大学)が “Changing Attitudes of MPs Opposing the Abolition of the British Slave Trade 1787-1807” というタイトルで報告を行った。本報告では、イギリス議会内で展開した奴隷貿易廃止法案をめぐる攻防に注目し、奴隷貿易廃止に反対した議員の投票行動と彼らの背景の関係が分析された。分析の結果、スコットランド選出議員と奴隷貿易廃止反対の関係を指摘するなど、西インド利害関係者だけでない奴隷貿易廃止反対の実態を検討する試みであった。質疑応答では、西インド/東インドといった語がはらむイメージに注意する必要があること、議論がイギリス本国の視点に偏っており、カリブ側から見た視点を導入する必要があること、奴隷に関する問題を扱うには人種の問題を取り上げる必要があることなどが提起された。また、スコットランドと奴隷制に関する近年の研究成果と本研究がどのような関係にあるのか、奴隷貿易廃止反対派の研究がどのような枠組みのなかに位置付けられるのか、グローバル・ヒストリーの文脈に置くとすれば、どのような意義があるのかなどが、議論された。
(文責・森井一真)
報告5
2019年9月4日(水)午後に、東京カレッジ・シンポジウム「アイデンティティのグローバルヒストリー」が開催されました。池亀彩氏(東京大学)が司会を務め、パネリストとしてアンドレアス・エッカート教授(ベルリン・フンボルト大学)、シルヴィア・セバスティアーニ教授(フランス国立社会科学高等研究院)、フィリップ・ノード教授(プリンストン大学)、羽田正教授(東京カレッジ)が登壇しました。
最初に、羽田教授によるシンポジウムの趣旨説明があり、羽田教授は政治や社会問題を論じる際によく使われるアイデンティティについて、グローバルな文脈で共同研究を行うことを提案しました。司会の池亀氏によるパネリストの紹介に続き、4人のパネリストがアイデンティティについて議論しました。
まず、世界史、グローバルヒストリーについて研究を進めている羽田教授は、従来の研究では、アイデンティティが世界のどこでも普遍的な概念として用いられてきたことを問題視し、例えば英語と日本語、スペイン語と日本語の間でもアイデンティティが指すものには違いがあるのではないかと述べました。さらに、アイデンティティという言葉が1960年代に日本に導入された経緯とその後の展開を紹介しました。
次に、スコットランドの啓蒙主義が専門のセバスティアーニ教授は、18世紀の後半のスコットランドにおいて、ラテン語のidemが語源となるアイデンティティは「同じでない」という意味でつかわれ、「多様性(diversity)」もアイデンティティとして考えられている近代とは反対の意味で使われていたと強調しました。ヨーロッパの国々が共通の道のりの中でどのように特異性を持つようになったのか、何がわれわれを結びつけ、何がわれわれを区別するのかという問題、普遍主義と特異性の緊張関係は今もなお続いていると述べました。
続いて、近現代フランス政治、文化史を専門とするノード教授は、エリック・エリクソンによる『Identity, Youth, and Crisis(アイデンティティ-青年と危機)』(1968年)、フェルナン・ブローデルによる『L’identité de la France(フランスのアイデンティティ)』(1986年)、ピエール・ノラによる『Les lieux de mémoire:La République(記憶の場)』(1984年)等の書籍を挙げ、アイデンティティという概念が精神分析学で個人に当てはめられたものから歴史的な分析で集団に転用されるようになったことを指摘し、これによって何が得られ、何が失われたのか分析しました。
最後に、アフリカ史を起点にグローバルヒストリー研究を展開するエッカート教授は、アフリカにおけるアイデンティティの事例を二つ紹介しました。一つ目の例として、1994年4月6日ルワンダの首都において起こった民族的大量殺人が、文化的差異の衝突にとどまらない政府という現代的な制度が準備した虐殺であったこと、より強固になった民族的なアイデンティティを示すものであったことを説明しました。二つ目の例として、1957年に独立したガーナの多民族ナショナリズムのモデルを挙げ、ナショナルアイデンティティに曖昧さがあると述べました。
シンポジウム後半では、フロアからの質問を交えて討論が行われました。司会の池亀氏は、アイデンティティをめぐる現在の政治的な状況をどう考えるかについて質問を投げかけました。パネリストらは、アイデンティティが歴史を通して構成されるものであると同時に、歴史を通して現実となり実態を持つようになり、人々がそれをベースに行動すると指摘しました。グローバルヒストリーの方法論を使うことで地球の住民としてのアイデンティティを強化することは可能なのかという議論に続き、学術界におけるアイデンティティとアクティビストのアイデンティティは区別するべきではないか、という意見や、日本のナショナリズム、スコットランドの啓蒙主義、ルワンダの大量殺戮といった多種多様なテーマをアイデンティティの問題と一括りにしてよいのか、よりふさわしい表現はあるのか等、様々な質問が挙がりました。
(文責:寺田悠紀)